「建設業って、休みが少なそう」──そう思っている方は少なくないかもしれません。朝が早くて、現場仕事で、カレンダー通りの休みは期待できない。そんなイメージが長年、建設業界につきまとってきました。しかし本当にそうでしょうか。働き方改革が進み、どの業界でも休日や労働環境を見直す動きが広がっている今、建設業もまた例外ではありません。
特に若い世代の就職・転職市場では「休日の充実」が大きな関心ごとになっており、企業側も「休みやすさ」を積極的に発信しはじめています。一方で、「年間休日が何日あれば多いのか?」という基準すら、業界ごとに異なるため、比較の仕方も重要です。
この記事では、建設業界の年間休日の現状と、企業ごとの違い、そして「休める建設会社」をどう見極めるかについて、事実に基づいて整理していきます。「建設業=休みが少ない」という先入観を持ったままでは、せっかくの選択肢を見落としてしまうかもしれません。
建設業の年間休日は平均何日?業界全体の傾向をチェック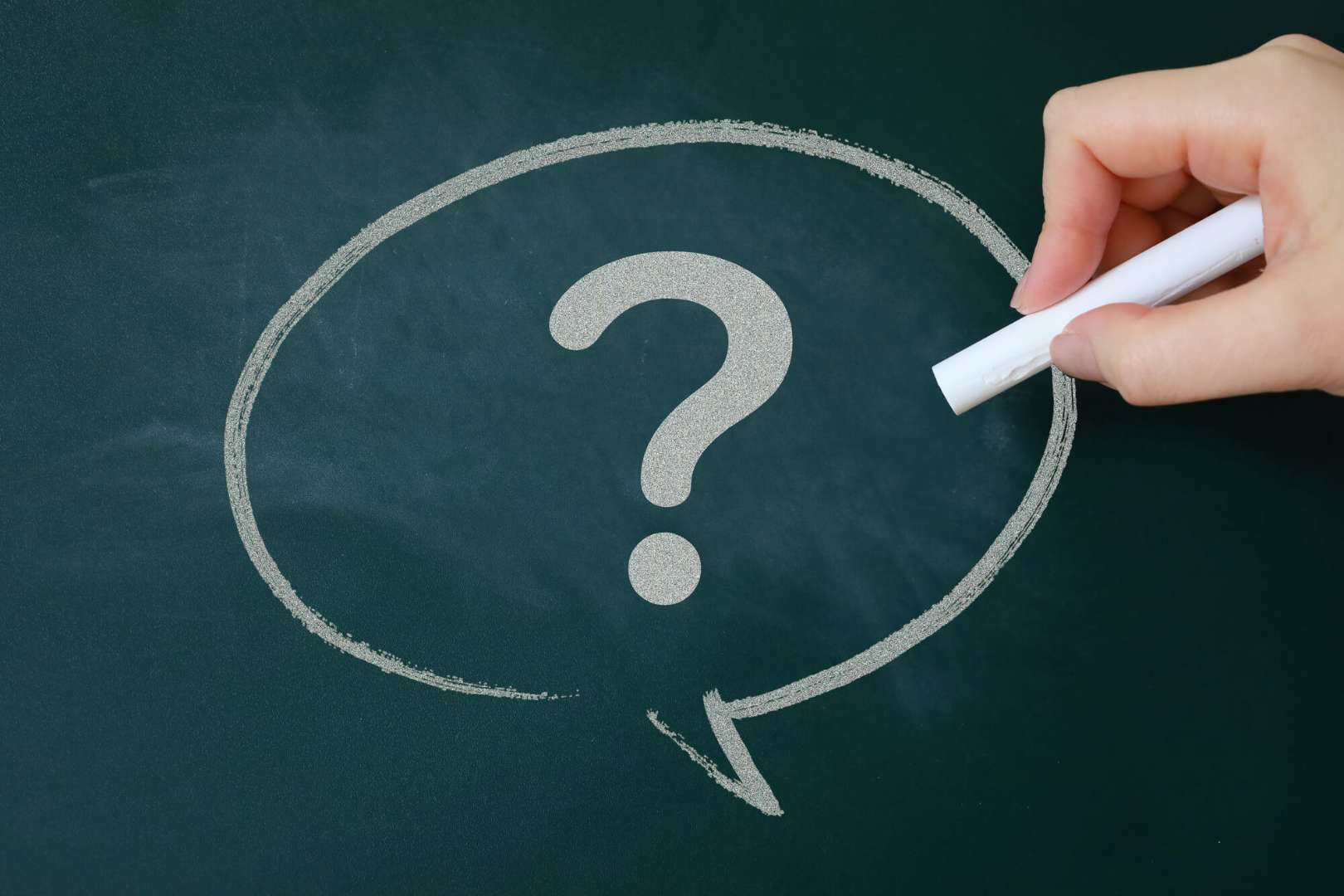
建設業は「休日が少ない」と言われがちですが、実際の年間休日数はどうなっているのでしょうか。厚生労働省が発表している「就労条件総合調査(2023年)」によると、全産業の平均年間休日は107.5日。一方、建設業の平均は約96.9日となっており、たしかに若干少ない傾向があります。ただしこれはあくまで全体平均であり、企業の規模や業務内容によって大きな差があります。
たとえば、公共工事や元請け業務を主とする企業では、週休2日制(完全または隔週)の導入が進んでおり、年間休日数が100日を超えるケースも少なくありません。また、労働時間管理が厳しくなった影響で、現場を担当する技術者の休日取得にも配慮されるようになってきています。特に若年層の採用を重視する企業では、就業規則やカレンダーの見直しに踏み出すところも増えています。
一方で、下請け比率が高い中小企業では、現場スケジュールに左右されるため柔軟な休日取得が難しいこともあります。繁忙期と閑散期の差が大きいという業界特有の事情もあり、「月によって休みの取りやすさが変わる」という声も聞かれます。
つまり、「建設業=年間休日が少ない」と一括りにはできません。平均より少なめの傾向はあるものの、企業ごとに制度や取り組みに差があるのが現実です。だからこそ、休日数だけでなく、取得のしやすさや現場の運営体制まで含めて確認することが重要になってきます。
職場によって大きく差が出る!会社ごとの休日制度とは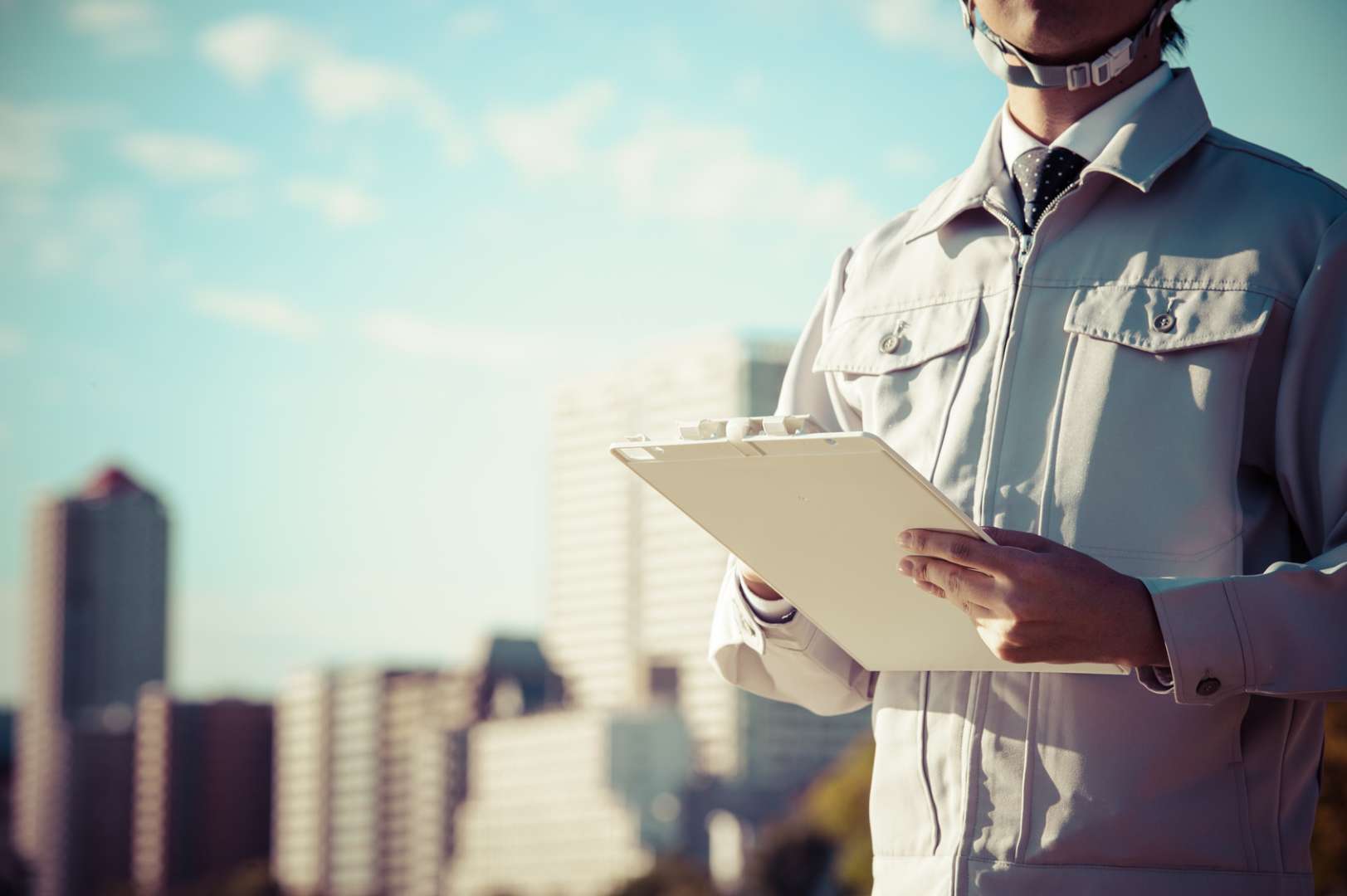
建設業の年間休日は、会社によって大きく差があります。これは業種や規模の違いというよりも、企業の方針や経営の考え方によるところが大きいのが実情です。たとえば、元請けとして現場全体を管理する企業は、工程を自社で調整できるぶん、計画的に休日を設定しやすくなります。そのため、週休2日制(毎週土日休み)や年末年始・夏季休暇の制度が整っているところもあります。
また、近年は建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及も後押しし、労働時間や休日の「見える化」が進んできました。労務管理を厳格に行う企業では、有給休暇の取得率や残業時間の実績も明確に開示されており、現場で働く技術者の安心感につながっています。
一方で、下請けや個人事業に近い形態の事業者では、現場のスケジュールに追われる形で休日取得が流動的になるケースもあります。工期が短く設定されている案件では、土曜日も作業が組まれることが多く、「隔週土曜休み」「月数回の休日」などのパターンになることも少なくありません。
つまり、同じ「建設業」というくくりの中でも、休日制度は会社ごとにまったく異なるということです。年間休日が明示されているか、有給取得を推奨しているか、現場に出ている社員と内勤社員で休日に差がないか——こうした点を確認するだけでも、企業の労務管理に対する姿勢をある程度見極めることができます。
求人票や企業ホームページでは「週休2日制」と記載されていても、その内容が「完全週休2日」か「隔週2日」かは明記されていないこともあるため、実際に面接や説明会などで確認するのが理想です。
「休める現場」はこう見極める!求人情報で確認すべき3点
建設業界で「休める職場」を見つけるには、求人票や企業情報を見る目が重要です。単に「週休2日」や「年間休日○日」といった表記に頼るだけでは、実際の働き方を正確に把握することはできません。休みやすさを見極めるためには、以下の3つのポイントに注目するのが効果的です。
まず1つ目は、「年間休日数の明示」があるかどうか。多くの求人票では「週休2日制」といった曖昧な表現が使われがちですが、本当に休める職場は年間休日数をしっかり数値で提示しています。110日以上を目安にすると、カレンダー通りの休みに近い働き方が想定されます。
2つ目は、「有給休暇の取得状況」です。実際に取得しやすいかどうかは、社内文化や現場体制によります。有給消化率を記載している企業や、「取得を奨励しています」と明記されている場合は、制度としてだけでなく実態としても機能している可能性が高いと言えます。
3つ目は、「現場ローテーションや直行直帰の有無」。複数の現場を掛け持ちしている会社でも、工程管理がしっかりしていれば休日を確保しやすくなります。反対に、現場の進捗に合わせて休日が変動する職場では、年間休日数が多くても実際の取得率が低くなるケースもあります。
これらの情報は、求人票だけでは把握しきれないことも多いため、企業の採用ページや社員インタビュー、現場の様子がわかるSNS投稿なども参考になります。また、気になる企業には実際に問い合わせをして「土日は本当に休めますか?」「長期休暇はありますか?」と質問してみることも、ミスマッチを防ぐ一つの方法です。
働き方改革で変わる建設業界。これからの休日制度は?
かつて「休めない仕事」の代名詞とされていた建設業界にも、確実に変化の波が訪れています。その大きな要因のひとつが「働き方改革」です。2019年の法改正以降、大手ゼネコンを中心に週休2日制の導入が進み、それに伴って協力会社や中小企業も休日制度の見直しを迫られるようになりました。
国土交通省は「建設業の週休二日推進工事」を設定し、発注者が率先して取り組むことで、受注者にも休みを確保するインセンティブを与える仕組みを整備しています。これにより、公共工事では土日休みを前提とした現場運営が進みつつあります。さらに、CCUS(建設キャリアアップシステム)の普及も後押しし、労務管理の透明化が進むことで、建設現場の働き方が少しずつ変わり始めています。
とはいえ、すべての企業で急激に改革が進んでいるわけではありません。人手不足や工程の都合上、まだ休みが取りにくい環境が残っている現場もあります。だからこそ、職場選びの際には「この会社はどれだけ未来を見据えているか」という視点が重要です。制度だけ整っていても、実際に使われていなければ意味がありません。逆に、小規模な会社でも、社長や所長が率先して休暇を推奨している現場なら、安心して働ける環境といえます。
建設業においても、ワークライフバランスを大切にする流れは着実に広がっています。これからこの業界に飛び込む方、あるいは転職を検討している方は、「休みやすさ」という軸を持って会社選びをしてみてください。
👉 週休2日や年間休日にこだわって働きたい方は、ぜひ岡田建設の採用情報をご覧ください。
https://www.okada-kensetu.jp/recruit
休日の多さが「働きやすさ」を決める時代に
働き方の価値観が変わりつつある今、「休めるかどうか」は仕事を選ぶ上で大切な基準のひとつです。建設業界でも、「厳しい」「休めない」といった過去のイメージから脱却しようとする動きが確実に進んでいます。実際、年間休日100日を超える企業や、有給取得を後押しする現場も増えてきました。
もちろん、工期や現場の都合で完全にカレンダー通りとはいかない場合もありますが、だからこそ会社選びには慎重さが求められます。「建設業だから仕方ない」とあきらめるのではなく、「建設業でも休める働き方ができる」ことを前提に、自分に合った職場を探す視点が大切です。
まずは、気になる企業の採用情報を見比べたり、実際に問い合わせてみたりするところからでも十分です。現場で働く自分をイメージしながら、休日や働き方に納得できる会社に出会えれば、建設業はもっと前向きな選択肢になるはずです。
▶ 岡田建設では、働きやすさを大切にした職場環境づくりに取り組んでいます。


